| 労働基準法の豆知識 |
|
|
|
| 社会保険のしくみ |
|
|
|
| 労働保険のしくみ |
|
|
|
| 定年延長・継続雇用制度 |
|
|
|
| 就業規則の基本事項 |
|
|
|
| 就業規則作成のポイント |
|
|
|
|

|
|
|
|
対象者基準の設定
|
 |
|
|
継続雇用制度(再雇用制、勤務延長制)の対象者は、どのように決めたら良いのでしょうか?
対象者の決め方には、以下の2つがあります。
継続雇用制度については、原則は希望者全員をその対象とすることが求められます。
ただし、例外として「労使協定」により継続雇用制度の対象となる労働者の基準を定めたときは、
その基準に該当する者だけを対象とすること、
つまり、希望者全員を対象としないということも認められるわけです。
さらに特例として、事業主が「労使協定」を結ぶために、労働者の過半数代表者と協議し、
努力したにもかかわらず、労使間の合意が得られない場合には、期限付き(図2参照)で、
労使協定によらなくても 就業規則などに対象者の基準を定めることが認められています。
【図2 就業規則で対象高年齢者基準を設定できる期間】
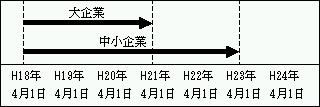
【対象者基準の具体的内容】
対象者基準の具体的内容をどのようなものにするかについては、原則として労使に委ねられていて、設定は自由です。
ただし、労使で十分に協議して定められたものであっても、
事業主が意図的に継続雇用を排除しようとするなど法規定の趣旨に反するもの、
他の労働関係法規や公序良俗に反する内容のものは認められないとされています。
対象者基準の選定基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいとされています。
- 意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること
(具体性)
→労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
- 必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること
(客観性)
→企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
|
|
|
|
>>就業規則って何? |
|
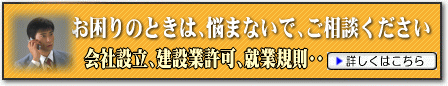 |
|