|
|
1年単位の変形労働時間制
|
 |
|
|
「1年単位の変形労働時間制」とは、1年以内の期間を単位として、その間の時季的な業務量の繁閑に応じて業務が繁忙する時期には所定労働時間を多く設定し、逆に閑散期には所定労働時間を少なく設定することで、労働時間を合理的に配分しようというものです。
1年単位の変形労働時間制のメリットを計画的に活用できるのは、年間カレンダーで労働日を決めている会社です。
例えば、1日の所定労働時間が8時間である場合、年間休日が105日あれば1週間を平均して40時間以内をキープすることができます。
|
|
|
|
|
労使協定の締結 |
|
この制度の採用に当たっては、労働者の過半数を組織する労働組合(このような労働組合がない場合は過半数代表者)との間で、次のような要件を書面で協定する必要があります。
|
|
| ① |
変形労働時間制によって、労働させる労働者の範囲 |
| ② |
対象期間(1年以内である必要) |
| ③ |
特定期間(対象期間中で、特に業務が繁忙な期間のこと) |
| ④ |
対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
ただし、対象期間を1ヵ月以上の期間ごとに区分するのならば、
(a) 最初の期間の労働日と各労働日ごとの労働時間
(b) 残りの各期間の労働日数と総労働時間を定めて、残りの期間については、各期間の初日の30日前までに労働者の過半数代表者や労働組合などの同意を得て特定する必要がある |
| ⑤ |
有効期間 |
|
|
|
|
|
労働日および労働日ごとの労働時間に関する限度 |
|
労働日および労働日ごとの労働時間に関しては、次のような限度があります。
|
|
| ① |
1日の所定時間の上限は10時間、1週は52時間以内であること |
| ② |
対象期間が3ヵ月を超える場合は次の条件を満たすこと
(a) 所定労働時間が48時間を超える週は連続3週以下であること
(b) 3ヵ月ごとに区分した各期間における所定時間が48時間を超える週の初日は3以下であること |
| ③ |
連続して労働させることのできる所定労働日数は6日を限度とすること |
| ④ |
特定期間の連続所定労働日数は、1週1日の休日が確保できる日数であること(12日が限度) |
| ⑤ |
対象期間が3ヵ月を超える場合の所定労働日数の限度は1年当たり280日であること |
|
|
|
|
割増賃金の対象は? |
|
1年単位の変形労働時間制を活用した場合に、時間外労働として割増賃金の支払いの対象となるのは次のような場合です。
|
|
| ① |
【1日について】
8時間を超える定めをした日はその時間を超えた時間、それ以外の日は8時間を超えた時間 |
| ② |
【1週について】
40時間を超える定めをした週はその時間を超えた時間、それ以外の週は40時間を超えた時間(①で時間外労働となった時間は除く) |
| ③ |
【対象期間について】
次の算式によって計算される対象期間における法定労働時間の総枠を超えた時間
(①、②で時間外労働となった時間は除く)
対象期間における法定労働時間の総枠
=40時間×対象期間の週の数(対象期間の日数÷7) |
|
|
|
|
>>健康保険とは? |
|
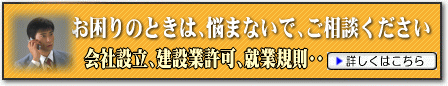 |