| 労働基準法の豆知識 |
|
|
|
| 社会保険のしくみ |
|
|
|
| 労働保険のしくみ |
|
|
|
| 定年延長・継続雇用制度 |
|
|
|
| 就業規則の基本事項 |
|
|
|
| 就業規則作成のポイント |
|
|
|
|

|
|
|
|
労使協定とは?
|
 |
|
|
労使協定の必要な制度 |
|
労使協定とは、労働基準法、育児・介護休業法等で定める事項のいずれかについて、使用者と労働者の過半数代表者とが協議して決め、締結内容を書面にした約束事のことです。
労働基準法等で労使協定の対象としている事項を下図にまとめて示します。
| 労使協定が必要な事項例 |
届出の必要性 |
| 貯蓄金の管理 |
○ |
| 賃金からの一部控除 |
× |
| 専門業務型裁量労働制 |
○ |
| 事業場外労働に関するみなし労働時間制 |
○ |
| 交替休憩の実施 |
× |
| 時間外労働・休日労働の実施 |
○ |
| 1ヵ月単位の変形労働時間制 |
○ |
| 1年単位の変形労働時間制 |
○ |
| 1週間単位の変形労働時間制 |
○ |
| フレックスタイム制 |
× |
| フレックスタイム制の下での時間外労働・休日労働 |
○ |
| 年次有給休暇中の賃金支払い(標準報酬日額) |
× |
| 年次有給休暇の計画付与 |
× |
| 育児休業制度の適用除外者 |
× |
| 介護休業制度の適用除外者 |
× |
| 65歳までの継続雇用制度 |
× |
※ ○印は労働基準監督署長への届出が必要 ×印は届出の必要なし
|
|
労使協定の刑事免責的効力 |
|
労働者を法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に出勤させるには、労使間で協定を結び、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
労使協定なしに法定労働時間のあとも残業させると、使用者は6ヵ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。
ところが「時間外労働に関する労使協定」を届け出てあれば、法定時間外労働違反で罰せられることはありません(労働基準法第36条)。
労使協定には法定義務違反の責めや罰を免れることができる効果があり、これを「刑事免責的効力」といっています。
しかし、労使協定には、労働協約や就業規則のように労働契約に勝る法規範としての効力(使用者と労働者を拘束する強制力)はないので、たとえ「36協定」が結ばれていても、これにより個々の労働者が法定時間外労働に従事する法律上の義務は生じません。
|
|
労使協定の締結は事業場単位 |
|
労使協定は会社一括でなく、就業規則と同じく事業場単位に結びます。
締結当事者は労働者側は「労働者の過半数代表者」です。
また、会社側は「使用者」です。
たとえば、複数の事業場がある企業の場合は、社長がなっても、各事業場の長(支店長、工場長など)がなってもかまいません。
|
|
|
|
>>36協定とは? |
|
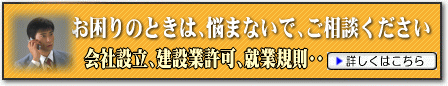 |
|