|
|
36協定とは?
|
 |
|
|
労使協定の必要な制度 |
|
残業させるには、事前に「36協定」の届出が必要 |
|
残業、休日労働をさせるためには、1日、1ヵ月、1年というスパンで従業員に何時間まで時間外労働をさせ、また、1ヵ月あたり何回まで休日労働をさせることができるのかについて、会社と労働者の過半数を代表する者との間で取り決めをします。
それを書面で協定し、労働基準監督署へ届け出る必要があるのです。
これが労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36(サブロク)協定」と呼んでいます。
こうした手続きの過程を経て初めて、「36協定の範囲内であれば所定労働時間を超えて勤務させても構いませんよ」というお墨付きが与えられるのです。
|
|
時間外労働の限度時間 |
|
時間外労働や休日労働について、労使で協議の上、その限度時間を決めなさいといっても、パワーバランスの関係上どうしても会社側の思惑が働いて長時間労働につながりかねません。
そうした問題を排除する理由から、厚生労働大臣は、労働者の福祉や時間外労働の動向などを考慮して一定の限度時間の基準を定めることとされています。
|
|
延長時間の限度などに関する基準
| |
限度時間 |
| 期 間 |
一般の労働者 |
1年単位の変形労働時間制 |
| 1週間 |
15時間 |
14時間 |
| 2週間 |
27時間 |
25時間 |
| 4週間 |
43時間 |
40時間 |
| 1ヵ月 |
45時間 |
42時間 |
| 2ヵ月 |
81時間 |
75時間 |
| 3ヵ月 |
120時間 |
110時間 |
| 1年間 |
360時間 |
320時間 |
|
|
特別条項付き36協定 |
|
臨時的に限度時間を超えて、時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、「特別条項付き協定」を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
|
|
「特別の事情」は「臨時的なものに限る」 |
|
平成16年4月に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」告示の一部が改正されて、特別の事情を臨時的なものに限るということが明確化されました。
通達(平15.10.22基発第1022003号)で、次のように運用方針を明らかにしています。
| ① |
「臨時的なもの」とは一時的または突発的に時間外労働を行なわせる必要があるもので、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであること |
| ② |
特別条項つき協定には、「1日を超え3ヵ月以内の一定期間」について特別延長時間まで延長できる回数を協定するものとする。
この回数は、特定の労働者について特別条項の適用が1年の半分を超えないものとする |
| ③ |
特別の事情については、できる限り詳細に協定すること |
| ④ |
協定に回数の定めがない場合は、特別の事情が臨時的なものであることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして助言指導の対象となること |
|
|
「時間外労働の限度時間」の適用除外 |
|
次の一定の業務については、特に長時間労働を行なう実態にあるため、前述の基準が除外されています。
①工作物の建設などの事業
②自動車の運転の業務
③新技術、新商品などの研究開発の業務
④厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます)
|
|
|
|
>>管理監督者とは? |
|
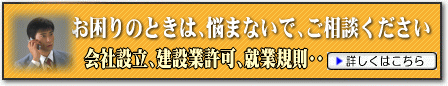 |